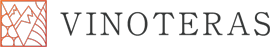5分でわかるオレンジワイン|インポーター厳選おすすめ3選

5分でわかるオレンジワイン特集。オレンジワインについて、製法やブドウの品種を解説します。インポーターおすすめのオレンジワインも5アイテム厳選。
目次
1.オレンジワインとは?
2.ジョージアワインとは?
3.国産のオレンジワイン
4.インポーター厳選!オレンジワイン
オレンジワインとは?
ここ数年で一気に広がりを見せている「オレンジワイン」。
ワイン通の中でも、その新しい味わいに虜になってしまう人が続出。自然派ワインを好む人からも注目されており、赤ワイン・白ワイン・ロゼワインに続くワインとして人気になっています。
今までのワインとは一味違う、オレンジワインとは?
オレンジワインの製造法や使われる品種、トレンドとなった理由を解説していきます。

オレンジワインが人気になった理由

オレンジワインの発祥地はジョージア。ジョージアはワイン造りに長い歴史があり、様々なワインを造っている中の一つにオレンジワインがありました。しかし、当時は旧ソ連の支配下にあったことからオレンジワインが国際的に市場に出回ることはありませんでした。
そんな中、ジョージアで造られていたオレンジワインにインスピレーションを受けたのがイタリアのグラブナー氏やラディコン氏。
彼らは90年代にはじめてオレンジワインを完成させました。このオレンジワインが高く評価されたことをきっかけに、他の国々でもオレンジワインが造られるようになりました。同時にジョージアで造られたワインの流通も盛んになり、今の人気に至ります。
オレンジワインの製法

「オレンジワイン」という名前から、オレンジから造られたフルーティーなワインが想像できますが、オレンジワインは白ブドウから造られているワインです。
オレンジワインを一言で言うと、「白ブドウ」から「赤ワインの製法」で造られたワイン。
白ワインは白ブドウをつぶした後、種や果皮を取り除いてから発酵させます。一方赤ワインは黒ブドウをつぶした後、種や果皮も一緒に発酵させた後にワインのみを抽出します。
赤ブドウの鮮やかな色は、この製法による黒ブドウの果皮からできています。
オレンジワインは、この赤ワインの製法により造られたもの。
白ブドウから造られているのにオレンジになるのは、赤ワインの製法のように種や果皮を一緒に発酵させることから来ています。
オレンジワインに使われるブドウ
オレンジワインでは、白ワインと同じく白ブドウが使われます。
その中でも、アロマティック品種といわれる白ブドウを使って造られているものが多くあります。
アロマティック品種とは、そのブドウ特有の香りが際立つ品種のこと。アロマティック品種の白ブドウによる豊かな果汁の香りと、その白ブドウからできるワインの香りが近いというのも特徴です。
品種としては、リースリングやゲヴェルツトラミネールなどが挙げられます。
ジョージアワインとは?
ワインの発祥地として注目のジョージア。オレンジワインもジョージアで造られたのが始まりです。
ジョージアのワインの歴史や、ジョージア独自の製造方法、ジョージアで造られているオレンジワインについて解説していきます。

ジョージアのワインの歴史

ジョージアは、東欧の南コーカサス地方に位置しています。
ソビエド連邦から独立したのが1991年。それ以降、ジョージアのワインの世界的流通が目立つようになりました。
ジョージアのワイン造りの歴史は、約8000年。紀元前6000年頃から続いています。
その頃は、コーカサス山脈から黒海のあたりでワイン造りが発達していたといわれています。
ジョージア独自のワインの製造方法

ジョージアのワインが注目されているのは、この長い歴史だけではなく独自のワインの製造方法も理由の一つです。
その製造方法は、「クヴェヴリ」を使用した独自のもの。クヴェヴリとは、粘土を素焼きして作られている卵型の壺を指します。
伝統的な製法の一つは、ブドウを木桶の中で踏みつぶして、果汁と一緒に果肉、果皮、種、果梗を全てクヴェヴリの中に投入。そのまま半年ほど発酵させます。その後、自然濾過を促すために別のクヴェヴリに中身を移した後に瓶詰め、または続けて熟成をします。
この間、クヴェヴリは地下の中で管理しています。土の中にあることでクヴェヴリの中身は低温に保たれ、発酵や熟成はゆっくりすすみます。
手間を加味して一時は減少していた製法ですが、2013年に「ユネスコ無形文化遺産」に登録されたことから、再度クヴェヴリによる製造方法は増加しています。
ジョージアのオレンジワイン

ジョージアでクヴェヴリを使用した製造方法では赤ワインや白ワインも作られていますが、代表的なのはオレンジワインです。ジョージアでは「アンバーワイン」とも呼ばれています。
国産のオレンジワイン
オレンジワインの流行の兆しは日本にも。ジョージアが発祥のオレンジワインですが、国産のオレンジワインもまた違った味わいが楽しめますよ。
オレンジワインに使われる国産の品種、国産のオレンジワインをご紹介していきます。

オレンジワインに使われる国産品種

日本でも流行の兆しが見られるオレンジワイン。
オレンジワインによく使われる代表的な国産品種には、甲州が挙げられます。
甲州
高い酸とほんのりとした甘みのある、落ち着いた味わいです。
甲州はノンアロマティック品種のため香りが強くなく、しばしば白桃やグレープフルーツのようだと表現されます。
甲州には、他のヨーロッパ系品種と比較して糖度が低いという特徴があります。近年では生産者やメーカーの努力によって糖度の高い品種も生まれていますが、糖度の低さをそのまま活かしたピュアな甲州など、様々な味わいがありますよ。
国産のオレンジワイン

オレンジワインは、赤ワインと同じように果汁と一緒に果肉や果皮、種、果梗も一緒に発酵させています。そのため、タンニンを含むポリフェノールが豊富で、日本では健康面からも注目されています。
【最新版】インポーターが厳選!オレンジワイン

世界の様々な国へ渡り、数多の生産者の中から厳選したワインを買い付けするインポーター。そんな仕入れのプロフェッショナルが、自社・他社問わずフラットな目線で選んだオススメワインをご紹介する斬新な企画。今まで試飲したワインの中から「本当に美味しい!」「心からオススメできる」と思えるワインのみをピックアップします。

山梨 祐樹
アズマコーポレーション営業/バイヤー
年間試飲本数1000本以上。ワインショップやレストランへ営業しつつ海外展示会へ買い付け。仕事・趣味共にワイン。家飲み大好きな32歳。
入門者にもオススメ。お手頃価格で楽しめるジョージア
出会ったのは試飲イベント。たまたま隣になったインポーターの方が「今これが売れているのですよ。」と、オススメしてくれたワインです。
個人的に当たり外れも多いイメージのジョージアですが、これは大当たり!しかもこのお値段。想像した価格よりも1000円程安く驚きました。
「悔しい!自分が先にこの生産者に出会って仕入れたかったな・・」と思ったのが素直な感想です。
奥行きがあり非常にバランス良くまとまった正統派な味わい。「オレンジワインに興味はあるけど少し高いかな」「まずは個性が強すぎないものから飲んでみたい」そんな入門者にもオススメしたい1本です。
実際に多くのレストランでもオンリストされており、価格・味わい共にオススメしたいワインの1つです。
〈番外編〉マニアック度は5ツ星!ワイン会で注目を集めたいあなたへ
最後はちょっと変化球。
オレンジワインではありませんが、製法が似ている兄弟ワインのご紹介です。
果皮と共に長期間発酵させるのがオレンジワインですが、コチラのワインは発酵前のジュースの段階で果皮と触れさせる“スキンコンタクト”という技法を使っています。
しかもフランスを代表する高級産地ブルゴーニュでは非常に珍しいピノグリ種を使用。
ワイン会やズーム飲みで紹介したら「おおー!面白いね〜。センスあるね!」なんて注目されること間違いありません!
【新入荷!】クリーンでありながら、しっかりとした骨格と複雑な香りが特徴
オレンジワインの新入荷をご紹介します!
生産者はアジェンダ・アグリコーラ・カステッロ・ディ・ステファナゴは、11世紀に造られた由緒ある城がワイナリー。ミラノの南70km、標高500mの丘陵地で、1810年から城を所有するのはバルファルディ家という貴族の家系です。現在のオーナーは、5代目のジャコモ・バルファルディ氏で、その弟のアントニオ氏が畑と醸造を取り仕切っています。所有する土地は135ha。そのうち葡萄の栽培を行っているのは20haのみ。平均収穫量は33~40hl/ha。葡萄畑の環境づくりとして自然の生態系を生かすために、畑以外の土地には森や池などが残されています。電力はソーラーパネルで太陽光を利用しているため、遠方から延びる送電線などはなく自然を邪魔しません。1998年にオーガニック認証を受けており、発酵は野生酵母のみを使用。添加するSO2も赤ワインでは10~40mm、白ワインでは30~50mmと最低限に抑えています。ワインはヴィーガン(醸造過程で動物性由来の成分は使いません)対象です。
いかがだったでしょうか?
赤・白・ロゼに続く第4の新ジャンルと言われるオレンジワイン。 今回ご紹介したワインは実際に1本飲んで見て「どれも間違いない。」と思えたワインです。もしまだオレンジワインを飲んだことがなく、少しでも気になった方はまずは1本飲んでみて下さい。僕と同じようにきっと世界が変わります。 〈 山梨 祐樹 〉