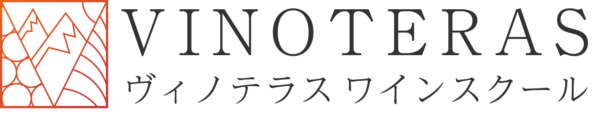ソムリエ・ワインエキスパート試験の一次と二次試験が終わった後は三次試験、サービス実技が待っています。
三次試験は、パニエに入れたワインを抜栓しデキャンタージュする という、最終の実技試験です。
「デキャンタージュ」はソムリエの仕事の中でも、1番と言っても良い見せ場のひとつではないでしょうか。
これまでの試験が難しかったからこそ緊張が最も高まる最終試験ですが、今回は試験までの残された時間を最大限に使い、「合格」というゴールに辿り着くための対策と準備についてご紹介いたします。



目次
- ソムリエ三次試験とは
- ソムリエ三次試験 合格のポイント
- 【重要】ソムリエ三次試験 実技の手順
- ソムリエ三次試験 合格への対策と準備 まとめ
ソムリエ三次試験とは

ソムリエ三次試験は、筆記試験の一次、テイスティングの二次を通過した方が最後に受ける実技試験で、論述とサービス実技があります。
「論述試験」は二次試験の日に受験し、合否は「サービス実技」と合わせた得点で審査されます。
長年、ソムリエ試験の最終試験は「デキャンタージュ」の実技となっており、ソムリエ協会が考える「良いサービス」を提供することが求められる試験です。
一次試験と二次試験に比べると合格率は高いので、焦らずに落ち着いて行えば問題はありませんが、デキャンタージュの一連の流れは何度か練習をしておかないと、緊張している中でスムーズに動くことは難しいです。
可能な限り、繰り返し練習することをおすすめします。
※二次試験免除の方は、二次試験日に論述試験のみを受験し、別日に三次試験を受けることができます。
2024年のソムリエ三次試験の日程は2024年11月18日(月)となっており、全国15箇所の会場で行われます。
ソムリエ三次試験 合格のポイント
- 受験票
- ソムリエナイフ
- リトー(トーション)
- ユニフォーム
- メモ帳と筆記用具
- 身だしなみ、清潔感
- 言葉遣い
- 表情、姿勢
サービスマンに求められる、清潔感のある身だしなみや、お客様に対する言葉遣い、姿勢がチェックされます。清潔なユニフォームを用意し、頭髪を整え、爪は短く切っておくようにしましょう。
試験を受ける際の服装に関しては、普段サービスをしている制服で良いのですが、ややカジュアルだと感じる場合は、スーツまたは白いシャツにスラックス、黒いエプロンを着用しておくと良いでしょう。
可能であればポケットの付いている服装がおすすめです。
スーツの内ポケットやエプロンのポケットにソムリエナイフやリトーをしまっておけますし、剥がした後のキャップシールをしまうこともできます。
スムーズに実技を行うためにも服装は重要ですので、自分に合ったユニフォームを用意しておきましょう。
会場での過ごし方
全国15箇所、ほぼ全てホテルなどの大きな会場で行われます。用意されている更衣室で着替えを済ませ、受験番号順に控室で自分の順番を待ちます。
更衣室と控室が大変混み合うことが予想されるので、早めに行って雰囲気に慣れておくのも良いですが、場合によってはかなり待つことがあるようです。
会場によっては待ち時間が長くなる可能性がありますので、待ち時間は実技手順のおさらいや、イメージトレーニングをして過ごすと、落ち着いた状態で本番に臨むことができるのではないかと思います。
【重要】ソムリエ三次試験 実技の手順

デキャンタージュが必要なワインのオーダーを受けたことを想定し、セラーからワインを取り出し、パニエに入れた状態で抜栓を行い、デキャンタージュをします。
ホストテイスティングをしていただき、グラスにワインを注ぐまでの一連のサービスを滞りなく行います。広い試験会場内にグループごとに分かれたテーブルがいくつか用意されており、1組4名〜6名に分かれ待機します。
試験官の「はじめてください」のアナウンスで、会場内の受験生が一斉にサービス実技をはじめます。
複数人が一斉にサービスをはじめるので、他の受験者の声や動きに注意を削がれ、何をしたら良いかわからなくなってしまう人も居るのですが、落ち着いて実技を行うようにしましょう。
試験時間は7分です。十分な時間はあるので焦る必要はありませんが、試験会場のどの位置に備品が置かれているのかは当日にならないとわからないので、不測に事態に備えて、練習の際は30秒から1分程度早く終わるイメージで練習をしましょう。
- 受験番号と名前を伝える
- オーダーを受ける
- ワインを取りに行く
- デキャンタージュの準備をする
- 道具をテーブルに並べる
- ワインの抜栓を行う
- テイスティング
- デキャンタージュ
- ホストテイスティング
- 片付け
- 実技終了
1.自分の受験番号と名前を伝える
試験官から「それでははじめてください」とアナウンスがあったら、試験開始となります。
2.オーダーを確認、復唱する
「かしこまりました、〇〇年シャトー〇〇でございますね、ただいまお持ちいたします」 試験官に向かって聞こえるようにはっきり伝える。
3.ワインを取りに行く
会場の隅にワインや備品が置いてあるコーナーがあるので、そこまで行き、ワインを静かにラベルが上になりようにパニエに入れ、テーブルに戻る。
お客様にワインをお見せしながら、
「ご注文をいただきました、〇〇年シャトー〇〇でございます。年代物のワインとなっており、少々オリがございますので、デキャンタージュをさせていただいてよろしいでしょうか」 と試験官に伝える。
(ボルドーの銘醸ワインで、古い年代のものをオーダーされることが多いが、若いワインをオーダーされる場合もあります。)
4.試験官が「お願いします」と言ったら、デキャンタージュの準備をする
備品が置いてある場所に移動し、トレーを左手に持ち、必要な備品をトレーに乗せていく。
<必要な道具>
- グラス2脚
- キャンドル(ライト)
- お皿2枚(デキャンタ、コルクを置くため)
- ナフキン2枚
- デキャンタ
グラスを乗せる際は、脚の部分を持ち、上にかざして汚れがないかを確認し、グラスの中に異臭が無いかも確認し、トレーに乗せる。
キャンドル(ライト)が点灯するかを確認しトレーに乗せる。 お皿2枚、ナフキン2枚をトレーに乗せる。
最後にデキャンタを手に取り、グラスと同様に曇りがないか、異臭はないかを確認する。(トレーに乗せても良いが、安定感が無いようならトレーに乗せずに右手に持ってテーブルまで運んでも問題ない)
5.テーブルに戻り、道具をテーブルに並べる。
デキャンタを左手側に置き、キャンドルを真ん中に置く。 お客様用のグラスと自分用のグラスを置き、お皿2枚(ボトル用とデキャンタ用)を並べ、ナフキンを置く。
6.ワインの抜栓を行う
ボトルをパニエに入れたまま抜栓する。 キャップシールを取り、取ったキャップシールはポケットに入れ、テーブルには置かないようにする。
キャップシールがとれたら、ボトルの口をナフキンで拭き取り、使用したナフキンもポケットにしまう。 抜栓後、コルクの香りを確認したら、スクリューからコルクを外し、コルクの香りを確認する。
「コルクは大変健全な状態です」と伝え、お皿の上に置く。 抜栓後もボトルの口をナフキンで拭き取る。抜栓前と抜栓後、2回拭き取ることがポイント。
◆合わせて読みたい記事 失敗したくない!コルクの開け方のコツを伝授
7.テイスティング
「少々、お味見させていただいてよろしいでしょうか」と確認し、パニエを極力動かさず、一口で飲み切ることのできる量をグラスに注ぐ。
色と香りを確認し、一口で飲みきる。 味わいのチェックが済んだら
「ワインは大変素晴らしい状態でございます」と伝える。
8.デキャンタージュ
ライトが付いているかを確認し、テーブルの中央に置く。
パニエからボトルを静かに抜き、ライトの光源と瓶の肩の部分、自分の目線が一直線になる位置にボトルとデキャンタを構え、ゆっくりとデキャンタージュを行う。
オリがある設定のワインの場合、ボトルの底から2センチ程度残した状態でデキャンタージュを終える。何度か練習をして、ボトルの角度を覚えておくと良い。
デキャンタージュが終了したら、ボトルはパニエに戻すか、コルクを乗せたお皿の上に一緒に乗せても良い。この時、ラベルはパニエならば上に、お皿の上ならお客様の方に向けて置く。
9.ホストテイスティング
持参したリトーを添え、お客様のグラスに少量注ぐ。 注いだあとは、すぐにデキャンタの口にリトーを添え、雫がこぼれないようにする。
「ホストテイスティングをおねがいいたします」とお声がけをする。
2秒ほど間をあけ、試験官が了承したことを前提に、改めてグラスに適量を注ぐ。
お皿の上にデキャンタを置き、「それでは、ごゆっくりお楽しみくださいませ」とお声がけし、下がる。
10.片付け
トレーに使い終わった自分用のグラスとパニエを乗せて、道具の置いてあるコーナに戻す。
11.実技終了
道具を戻したら再びデーブルに戻り、「ただいま終了しました」と試験官に伝え終了。
- 試験がはじまる前に、ワインと備品の位置を確認しておく
- 必要なプレゼンテーション(セリフ)は暗記しておく
- 周りの声や動作を気にせず、落ち着いて練習通りに行う
- グラスやデキャンタは天井の光に照らして汚れていないか確認をする
- 抜栓前と抜栓後、ボトルの口は2回拭き取る
- オリを残す想定のワインの場合は2cmほど残し、若いワインの場合は残さず全て注ぎ切る。
- グラスに注ぐ際、ボトルの口にリトーを添える
- 少し早めの時間で終わるように練習の際は時間を測って行う

オーダーされたワインが若いワインという設定だった場合
サービス実技では、ボルドーの銘醸ワインの、古い年代のものをオーダーされることが多いですが、まれにオリの無い若い年代のワインを頼まれる事があります。
その際は、オリを取り除くためではなく、香りを開かせるためにデキャンタージュを行いますので、実技の中でのセリフが変わってきます。
「ご注文をいただきました、2020年シャトー○○でございます。大変若いワインのため、デキャンタージュをすることにより、より香りが引き立ちますので、デキャンタージュしてもよろしいでしょうか?」
上記のようにセリフを変え、ワインは残さずデキャンタに注ぎ切りましょう。
試験官によって、セリフやアクションごとに頷いてくれる方、特にリアクションの無い方がいますが、気にせず一連の流れを続けましょう。
ソムリエ三次試験 合格への対策と準備 まとめ

当日は緊張で頭が真っ白になり、プレゼンテーションのセリフが飛んでしまった、という方も少なくないようです。
入念に練習を重ねても、ところどころセリフを忘れてしまったり、確認を飛ばしてしまったり、諸先輩方の話を聞いていても皆様何かしらのミスや漏れがあるようです。
三次試験は落とすための試験ではありませんので、途中でミスに気付いても、最後まで堂々とやり切りましょう。
私が受験した時の最終試験では、練習では一度もこぼさなかったにも関わらず、本番で盛大にワインをこぼしました。おそらくボトルの5分の1くらいの量はこぼしていたと思います。
さらに、ワインと備品が別々の場所にあるというイレギュラーにも見舞われ、散々な実技試験でしたがなぜか合格することができました。
配点のポイントは一箇所だけではありませんので、1つや2つのミスは全く問題ありません。
2024年度の三次試験は11月18日(月)です。
今回紹介した実技のポイントをしっかり押さえて、可能であれば本番と同じ服装で練習をし、本番に臨みましょう。
一次と二次を通過することができたなら、ソムリエに必要な資質は十分にあるはずです。資格を取った後に何をしていきたいのかを考え、ぜひ合格を掴み取ってください。
■ヴィノテラスではソムリエコンクールファイナリストの佐々木健太氏によるソムリエ三次試験対策の対策講座を実施しています。実演動画もありますのでテスト直前まで何度でも動画を見て復習が可能です。試験を目前に控えた受験生の方、必見です!
▼試験対策にご活用ください▼