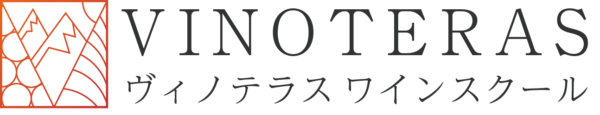ソムリエ・ワインエキスパート試験の一次試験が終わった後は二次試験、テイスティング実技が待っています。
テイスティングは慣れも必要ですので、一次試験の結果を待たず、すぐに二次試験対策に取り掛かることをおすすめします。
テイスティングといえば、銘柄を当てなくてはいけない…というプレッシャーを感じてしまう方も多いのではないかと思いますが、出題の傾向を知り、事前にしっかりと準備を行えば初心者でも合格することができます。
本来、ワインの表現に正解はありませんが、ソムリエ試験に関してはおおまかなパターンがあり、
傾向を掴むことができれば決して難しい試験ではありませんので、試験対策を通して楽しみながら勉強していきましょう。



目次
- ソムリエ・ワインエキスパート試験の流れ
- 過去の出題傾向と合格率
- ワインのタイプ別勉強方法
- テイスティングの準備
- 白ワインのテイスティング対策
- 赤ワインのテイスティング対策
- ワイン以外の飲料の勉強方法
- ソムリエ・ワインエキスパート 試験当日の過ごし方
- ソムリエ・ワインエキスパート 二次試験対策のまとめ
ソムリエ・ワインエキスパート試験の流れ
ソムリエ試験は一次試験から三次試験まで、ワインエキスパートは一次試験と二次試験を通過すると晴れて合格となり、二次試験ではソムリエ・ワインエキスパートともにテイスティングの試験となります。
| 資格呼称 | 一次試験 | 二次試験 | 三次試験 |
|---|---|---|---|
| ソムリエ | 筆記試験 | テイスティング:40分 ワイン3種、その他2種 | 論述・サービス実技 |
| ワインエキスパート | 筆記試験 | テイスティング:50分 ワイン4種、その他1種 | ― |
二次試験は例年10月に開催されています。
例年、ソムリエはワイン3種、ワイン以外の酒類1種、ワインエキスパートはワイン4種、ワイン以外の酒類1種をテイスティングし、外観や香り、味わいのコメントを解答欄に記載されている選択肢から選んで回答する試験です。
過去の出題傾向と合格率
日本ソムリエ協会が発表している、ソムリエ・ワインエキスパート試験 直近5回の合格率は以下のとおりです。
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ソムリエ | 17.7% | 30.1% | 42.1% | 37.9% | 29.8% |
| ワインエキスパート | 41.9% | 32.9% | 40.7% | 43.3% | 44.2% |
過去5年の出題
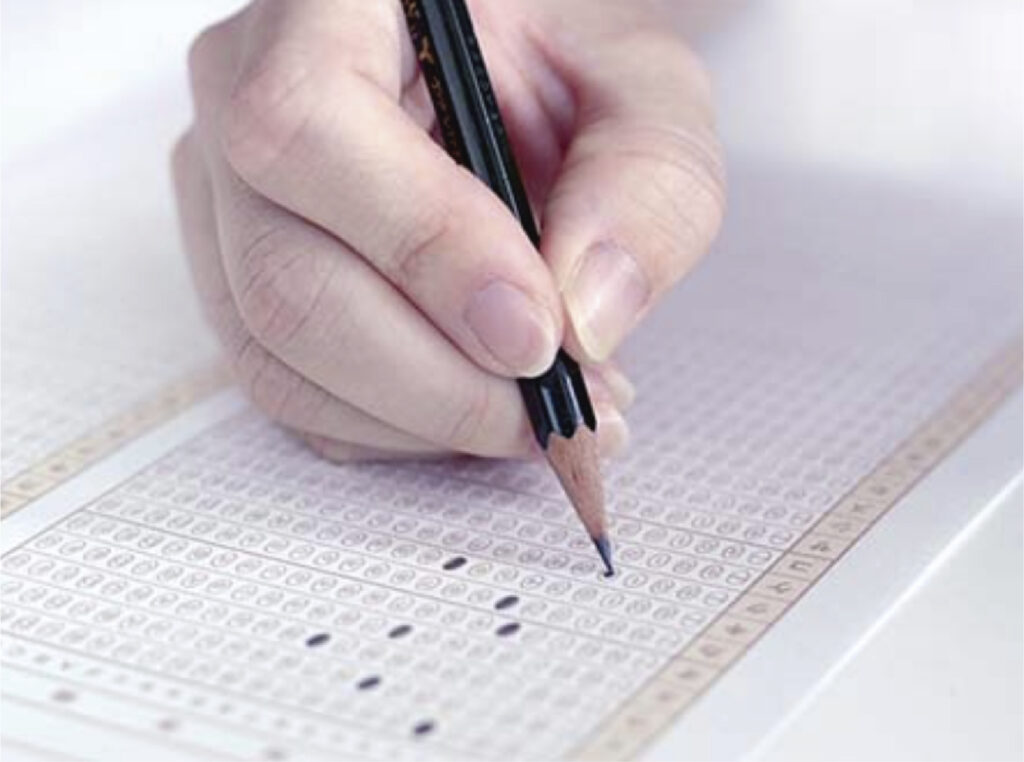
年代別 過去出題一覧
| 出題年 | 資格呼称 | 国 | 品種 | 生産年 | その他のお酒 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ソムリエ | フランス | ソーヴィニヨンブラン | 2021 | |
| アルゼンチン | マルベック | 2020 | |||
| 日本 | メルロ | 2018 | |||
| ドライベルモット | |||||
| スコッチウイスキー | |||||
| 2023 | ワインエキスパート | チリ | ソーヴィニヨンブラン | 2021 | |
| オーストラリア | リースリング | 2021 | |||
| フランス | グルナッシュ | 2021 | |||
| スペイン | テンプラニーリョ | 2017 | |||
| ジン | |||||
| 2022 | ソムリエ | フランス | シャルドネ | 2020 | |
| ドイツ | リースリング | 2019 | |||
| オーストラリア | シラーズ | 2020 | |||
| ピスコ | |||||
| イエガーマイスター | |||||
| 2022 | ワインエキスパート | ニュージーランド | ソーヴィニヨンブラン | 2019 | |
| 日本 | 甲州 | 2021 | |||
| アメリカ | カベルネソーヴィニヨン | 2019 | |||
| フランス | シラー | 2018 | |||
| オードヴィードキルシュ | |||||
| 2021 | ソムリエ | フランス | シャルドネ | 2019 | |
| イタリア | サンジョヴェーゼ | 2018 | |||
| アメリカ | メルロ | 2017 | |||
| ラム | |||||
| ヴェルモット | |||||
| 2021 | ワインエキスパート | フランス | リースリング | 2019 | |
| フランス | ヴィオニエ | 2019 | |||
| スペイン | テンプラニーリョ | 2017 | |||
| チリ | カベルネソーヴィニヨン | 2018 | |||
| テキーラ | |||||
| 2020 | ソムリエ | フランス | ソーヴィニヨンブラン | 2018 | |
| 日本 | シャルドネ | 2016 | |||
| イタリア | ネッビオーロ | 2017 | |||
| ホワイトポート | |||||
| ウォッカ | |||||
| 2020 | ワインエキスパート | アルゼンチン | トロンテス | 2019 | |
| フランス | シャルドネ | 2018 | |||
| フランス | カベルネフラン | 2018 | |||
| ニュージーランド | ピノノワール | 2018 | |||
| ラム | |||||
| 2019 | ソムリエ | フランス | アリゴテ | 2016 | |
| アメリカ | カベルネソーヴィニヨン | 2016 | |||
| スペイン | テンプラニーリョ | 2014 | |||
| 梅酒 | |||||
| ジン | |||||
| 2019 | ワインエキスパート | ニュージーランド | ソーヴィニヨンブラン | 2018 | |
| 日本 | 甲州 | 2017 | |||
| イタリア | サンジョヴェーゼ | 2015 | |||
| オーストラリア | カベルネソーヴィニヨン | 2015 | |||
| 紹興酒 |
出題されるブドウ品種の傾向
最近の出題から見ると、出題されるブドウ品種が難化している傾向にあるといえます。
ソムリエ・ワインエキスパート二次試験の合格するためには、たくさんの品種を飲み、手を広げていくよりも、基本となる主要品種の対策を徹底することです。
試験は品種当てゲームではありませんので、品種や生産年以上にテイスティングコメントの正確さが重要視されます。色や粘度といった外観、香りの系統、酸度、タンニンの強さ といった要素を的確に感じ取るようになることが、合格への近道となります。
例年、ソムリエ・ワインエキスパート二次試験は、会場に並べられたワイン・ワイン以外の酒類のテイスティングを行い、テイスティングコメントシートに記載されているコメントの中から、適切なものを選びシートに回答を記入していきます。
主な選択肢
- 外観
- 香り
- 味わい
- 評価
「外観」
外観の選択肢は、「清澄度」「輝き」「色調」「濃淡」「粘性」「外観の印象」に分かれています。
分類ごとに複数の選択肢の中から、適切なものを選んで回答をしていきます。
「清澄度」は「澄んだ 又は 濁った」、「輝き」は「輝きのある」など、
テイスティングしたワインに適したコメントを選択していきます。
「香り」
香りはおおまかに「第一印象」「フルーツ」「花」「ハーブ・スパイス」「ミネラル」「その他」などの項目に分かれており、外観と同様にテイスティングしたワインに適した香りの印象をコメントシートに記入していきます。
「味わい」
「アタック」「甘み」「酸味」「アルコール度数」「渋み」「苦味」「バランス」「余韻」などの項目に分かれており、これまでの項目と同様にテイスティングしたワインに適した香りの印象をコメントシートに記入していきます。
「評価」
「外観」「香り」「味わい」「サービス」で選んだ項目を踏まえて、結論としてヴィンテージ、産地、品種を割り出していきます。
そのワインの全体の印象を選ぶ項目や、最適な提供温度、グラスの大きさを選ぶ項目もあり、産地や品種よりも「外観」「香り」「味わい」が占める配点の割合が非常に多く、全体の6割以上に上ります。
ワインのタイプ別勉強方法
ソムリエ・ワインエキスパートの二次試験対策では、基本品種と呼ばれる主要6品種(カベルネ・ソーヴィニヨン、シラー(シラーズ)、ピノ・ノワール、シャルドネ、リースリング、ソーヴィニヨン・ブラン)の対策が不可欠です。
最近の出題ではイタリアのサンジョヴェーゼや、日本の甲州など、基本品種には含まれていない品種も多く出題されていますが、基本品種以外に手を広げるのはこれらの品種の理解ができてからにしましょう。
仮に、飲んだことのない品種が出題された場合、品種がわからなくてもブドウの系統がわかれば「外観」「味」「香り」のコメントが共通します。配点の大半を占める「外観」「香り」「味わい」の選択肢が
合っていれば、品種は間違っていたとしても合格できる可能性が高まります。
テイスティングの準備
- テイスティングシートの用意する
試験と同様にテイスティングコメントを用意した状態でテイスティングをしましょう。 - グラスは同じ形のものを使う
自宅で飲む場合は、可能であれば同じグラスを使用しましょう。
- 2種類以上のワインを比較してテイスティングする
赤ワインで違う品種、同じ品種で別の産地 など、比較することで違いがよりわかるようになります。
- 単一品種のワインで2000円~3000円程度のものを選ぶ
資格試験に出題されるワインと同じ価格帯のものを選ぶと、より本番に近い状態で練習ができます。
白ワインのテイスティング対策

白ワインのテイスティング対策では、主要品種3種類の他に、押さえておきたい3種類の特徴を把握することが大切です。
主要品種の違いを理解してから、押さえておきたい3品種のテイスティングに進むと、スムーズに理解ができるのではないかと思います。
主要品種3品種
・シャルドネ(フランス/アメリカ)
・ソーヴィニヨン・ブラン(フランス/ニュージーランド)
・リースリング(ドイツ/フランス)
押さえておきたい3品種
・甲州(日本)
・ミュスカデ(フランス)
・ゲヴュルツトラミネール(ドイツ/フランス)
主要品種3品種のテイスティング対策
・シャルドネ(フランス/アメリカ)
シャルドネはブドウ自体の個性はあまり無い品種です。
醸造方法や産地、樽由来の香りや味わいの特徴に焦点を当てると良いでしょう。
<おすすめ比較テイスティング>
・フランス産とアメリカ産の比較
・マコンとブルゴーニュのフランス内での別の産地での比較
・樽香のあるものと無いものの比較
・ソーヴィニヨン・ブラン(フランス/ニュージーランド)
ソーヴィニヨン・ブランは、ハーブ思わせる爽やかな香りが特徴のワインです。
比較的品種の特性が強く出るタイプの品種なので、理解しやすいのではないでしょうか。
<おすすめ比較テイスティング>
・フランス産とニュージーランド産の比較
どちらもソーヴィニヨン・ブランの主要産地で、産地による違いも非常に分かりやすく、品種の個性を掴むことができます。
・リースリング(ドイツ/フランス)
リースリングはソムリエ・ワインエキスパート二次試験での出題率が非常に高い品種のひとつです。
独特のミネラル感と、冷涼な気候が由来のキリッとした酸が特徴です。
<おすすめ比較テイスティング>
・ドイツとフランスの比較
押さえておきたい3品種のテイスティング対策
・甲州(日本)
・ミュスカデ(フランス)
甲州とミュスカデを比較して飲んでみるのもおすすめです。色の違いを比べてみると非常に分かりやすく、甲州はグレーやベージュがかったような色味が特徴。
・ゲヴュルツトラミネール(ドイツ/フランス)
バラやライチのような香りが特徴のゲヴュルツトラミネールは、非常に品種の特徴がよく出たワインで、一度はチェックしておくと良いでしょう。
赤ワインのテイスティング対策

赤ワインの主要3品種は必ず出題されます。
主要3品種のテイスティング練習をしたら、押さえおきたい3種類もテイスティングし、対策をしておくと良いでしょう。
主要3品種
・カベルネ・ソーヴィニヨン(フランス/アメリカ)
・ピノ・ノワール(フランス/アメリカ)
・シラー(シラーズ)(フランス/オーストラリア)
押さえていきたい3品種
・サンジョヴェーゼ(イタリア)
・ガメイ(フランス)
・テンプラニーリョ(スペイン)
主要品種3品種のテイスティング対策
・カベルネ・ソーヴィニヨン(フランス/アメリカ)
出題回数が最も多いブドウ品種です。深みのある濃い色合い、黒い果実を思わせる香りと、樽熟成による香りが強く出るワインが多いです。
<おすすめ比較テイスティング>
・カベルネ・ソーヴィニヨン主体のボルドーワインを比較
・アメリカとフランスの単一品種のワインを比較
フランス産のカベルネ・ソーヴィニヨンをテイスティングし、慣れてきたところで、出題回数の多いアメリカ産と比較をすると違いを感じ取りやすいです。
・ピノ・ノワール(フランス/アメリカ)
基本品種であるピノ・ノワールも過去の出題率は高い品種で、透明感のある赤い色をしています。
<おすすめ比較テイスティング>
・ブルゴーニュとアメリカ産の比較
ブルゴーニュの他、フランス国内の別の産地との比較もわかりやすい品種です。
・シラー(シラーズ)(フランス/オーストラリア)
濃い色調とスパイシーな風味が特徴のシラーは、オーストラリア産の出題が多い傾向にあります。
<おすすめ比較テイスティング>
・フランス産(コート・デュ・ローヌ)とオーストラリア産の比較
スパイシーさとフルーティーさのバランスに加え、産地由来の特徴を比較しましょう。
押さえておきたい3品種のテイスティング対策
・サンジョヴェーゼ(イタリア)
カベルネよりも明るい赤系の色と、果実味と酸のバランスが特徴的な品種です。
・ガメイ(フランス)
イチゴの香りや粘性の少なさが特徴のガメイは、似た系統であるピノ・ノワールと比較すると違いを捉えやすいです。日本の品種であるマスカット・ベーリーAも、ガメイと同系統のテイスティング結果となります。
・テンプラニーリョ(スペイン)
樽の香りが特徴的なテンプラニーリョは、同じく樽香のあるカベルネ・ソーヴィニヨンと比較すると、単体で飲むよりも違いを捉えやすくなります。
ワイン以外の飲料の勉強方法
昨年度のソムリエ・二次試験で、その他の酒類に「ピスコ」というペルー原産のブドウの蒸留酒が出題され話題になりました。
知名度の低いお酒が出題されることも多い「ワイン以外の飲料」は、酒精強化ワイン、スピリッツ、ブランデー、リキュール、ウイスキー などの中から例年ソムリエでは2種、ワインエキスパートでは1種出題されます。
ワイン以外の飲料は、ワインに比べそこまで重要ではありませんが、ソムリエの場合は5種のうち2種がワイン以外の飲料から出題されるため、最低限の対策は必要になります。
過去に出題されたワイン以外の飲料で、飲んだことのないものを確認し、
その他に「日本ソムリエ協会 教本」に記載のある酒類で、見たり飲んだりしたことが無いものは、インターネットで外観や色を確認しておくのも良いでしょう。
可能であれば、上記の中からいくつかピックアップし、バーや居酒屋で飲んでみるというのがおすすめです。
テイスティングに自信が持てない時は、ワイン以外の飲料に時間をかけるよりも、主要品種のテイスティングに時間をかけたほうが合格の可能性は高くなります。
ワイン以外の酒類は出題範囲が広く、種類が膨大にあり勉強しだすとキリがありませんので、ワインのテイスティングに疲れた時、息抜き程度に飲んでみる、というのも良いのではないでしょうか。
ソムリエ・ワインエキスパート 試験当日の過ごし方

ソムリエ・ワインエキスパート二次試験は、例年各地のホテル等の会場で行われます。
実体験や受験者の口コミから、試験当日の注意点をご紹介します。
- 普段通りに過ごす
- 直前に歯磨き粉で歯磨きしない
- 寒さ対策をする
- 早めに会場に着くようにする
- テイスティングのコツと時間配分
普段通りに過ごす
どの試験でも共通することですが、あえていつも通りに過ごしましょう。焦ってしまって新しい項目を勉強し始めたりするのは厳禁です。
いつものノートやメモ帳、参考書で復習をするようにしましょう。
直前に歯磨き粉で歯磨きしない
直前に歯磨きをするときは、歯磨き粉を使わないようにしましょう。
当日は緊張しているため、うっかり歯磨き粉を使わないように気をつけてくださいね。
寒さ対策をする
ソムリエ・ワインエキスパートの二次試験会場は冷房がかなり効いていて、寒いことが多いようです。
自分自身の防寒対策を忘れないようにしましょう。
また、ワインも冷えて香りが立たなくなっている可能性があります。
ワインが冷えすぎている場合は、グラスを覆うように手を添え、軽く温め温度をあげましょう。
早めに会場に着くようにする
例年ソムリエ・ワインエキスパート二次試験では、試験開始前からワインがテーブルに並んでいるケースが多いです。
早めに会場に到着することで、ワインの外観をじっくり観察する時間が取ることができ、かなり有利になります。試験開始後は時間との戦いですので、開始までに外観の観察を終え、余裕をもって香りや味わいのテイスティングに時間を割くことができます。
テイスティングのコツと時間配分
二次試験の試験時間は、ソムリエは40分、ワインエキスパートは50分となっています。
5問の出題に対し、8分〜10分程度しか解答の時間が取れないので、一次試験と同様にスピード感も重要になります。
テイスティングは必ず白ワインから、次に赤ワイン、最後にワイン以外の飲料 という順番で行うようにしましょう。
ワイン以外の飲料はアルコール度数が高い可能性が高いので、先に飲んでしまうとワインの繊細な香りをとることが難しくなってしまい時間のロスになってしまいます。
お酒があまり強くない方は吐き出すための紙コップもあるので、吐き出すようにしましょう。
ワインと一緒に水も配られますが、会場によっては、水がなくなったら注いでくれるところと、空になったグラスはそのまま、という会場もあるようです。
合格のためには、テイスティングコメントを埋めることを優先しましょう。たとえ品種がわからず悩んでも、まずは埋めて次の問題に取り掛かり、時間配分には常に注意しましょう。
ソムリエ・ワインエキスパート 二次試験対策のまとめ

限られた時間の中で、ソムリエ・ワインエキスパート二次試験の合格を目指すには、ポイントを押さえた試験対策が必要になります。
基本の主要品種に絞ったテイスティングのトレーニングと、教本や書籍で指定されたテイスティングコメントからコメントを選ぶ練習を続け、それぞれの品種のポイントを押さえることができれば、二次試験対策は独学でも十分合格を目指すことができます。
ソムリエ・ワインエキスパート試験は試験期間も長く、緊張状態が続く苦しい時期ではありますが、ソムリエを受験しない限り、ここまで真剣にワインを飲む事もないのではないかと思うと、とても貴重な経験と時間になるはずです。
職業としてワインに携わる方にとっては、資格取得後も勉強の日々かと思いますが、試験勉強でしか触れない部分は今後の見聞を大きく広げてくれますし、資格は取ることによって自信を持つことができます。
一次試験とは違った緊張感ですが、二次の方がはるかに楽しかったのを覚えています。
合格目指して頑張ってくださいね!
▼試験対策に是非ご活用ください▼