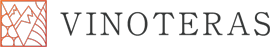ブドウの生育サイクルと栽培作業のなぜ ビュタ―ジュ(土寄せ)と畝くずし(デビュタ―ジュ)の必要性とは

ソムリエ教本の前半に少しだけ登場するビュタ―ジュ(土寄せ)とデビュタ―ジュ(畝くずし)。
土寄せと畝くずしという作業はぶどうだけに行われているのではなく、
野菜づくりには欠かせない作業となっています。
今回は土寄せと畝くずしの必要性について、少し掘り下げていきたいと思います。
目次
- ビュタージュ(土寄せ)とはどんな作業?その効果は?
- デビュタージュ(畝くずし)とはどんな作業?その効果は
- どの仕立ての樹にも必要なのか
- 土寄せと畝くずしは大事な工程

ビュタ―ジュ(土寄せ)とはどんな作業?その効果は?
ブドウの育成の中で11月~12月に垣根の土寄せを行うとありますが、それは何のためにするのでしょうか?
またせっかく土寄せを行ったのに、なぜ4月には元に戻すのか。
この作業をするのとしないのではブドウへの影響は変わってくるのか?
野菜づくりには欠かせない栽培管理の一つである土寄せという作業は、
ぶどうの樹の他にも葉物野菜や根菜類、ネギなどの茎葉類を栽培する時にも行われています。
栽培する野菜によって土寄せを行う目的は様々ですが、共通しているのは
根が露出してしまい株が倒れるのを防ぎ、追肥を合わせて行うことで養分を吸収させ生育を促進させる事。
野菜の種類によって土寄せを行うタイミングや回数、土の深さは様々で、
ジャガイモは日光に当たってしまうと緑化してしまうのでこまめに土寄せを行い、
ネギなどは白い部分を伸ばす目的で土寄せが行われます。
ソムリエ教本にも載っているように、ブドウの樹に行う土寄せは11月から12月頃で、
秋の収穫後、本格的な寒さがやってくる前に霜から樹を守るために行われます。
寒さへの対策をしていないと休眠期に樹が枯れてしまい、収量の減少につながります。
その他にも、雑草を生えにくくし水捌けを良くするという効果もあり、土寄せは他の野菜と同様にブドウの樹にとっても欠かせない作業です。

デピュタ―ジュ(畝くずし)とはどんな作業?その効果は?
畝くずしは休眠期を終えた萌芽から展葉期に行われ、ブドウの樹の他にも野菜を栽培する時に行われる作業です。
野菜の栽培をするときの畝くずしの目的は、同じ位置で栽培を繰り返すとその部分の肥料濃度が上がってしまい、
結果として発芽率が落ちてしまうため、畝の位置を変える目的で行われます。
ブドウ畑の場合は、畝くずしを行うことで冬の間に固まった地面がほぐされ、空気が加わることで水捌けも良くなり、
固まった土をほぐす作業に合わせて、雑草の新しい芽を取り除くことができます。
どの仕立ての樹にも必要なのか
仕立て方の違いや産地、生産者の考え方や樹齢によって土寄せを行わない場合もあります。
棚作りなど樹が高く成長している場合は、藁を樹に巻き付けるなどして冬囲いをし、
より自然な造りを目指している場合や、樹齢の高い樹を植えている区画はあえて耕起をしない
というところもあります。
特徴的な例として、北海道の一部地域を除く雪の多い土地では、土の代わりに積雪でブドウの樹を覆い、外気温からブドウの樹を守ります。
その年の冬の気温や、仕立て、樹齢、囲いを外すタイミング などの様々な要素よって得られる結果は違い、生産者ごとにいろいろな方法が採られています。

土寄せと畝くずしは大事な工程
ソムリエ教本にも出てきますが、さっと目を通していた土寄せと畝くずし。
ブドウを栽培する際の大事な工程だったのですね。
北海道の場合は、先述した通り雪の少ない一部の地域を除いて、土ではなく雪の中に樹を埋めて冬を越します。
雪の量は多すぎると重みで樹が潰れてしまい、少なすぎても樹が雪に守られずに寒さで枯れてしまうため、ブドウの樹も雪の重さを逃すため斜めに植えられています。
北海道は今がまさに結実期で、初夏に花が咲き小さな房が形成されると、
いよいよ生育期が始まりワイナリーは慌ただしくなってきます。
開花は冬の期間を無事に越すことができたという一つのサインで、
小さな花が咲いたのを見て生産者はほっと胸を撫で下ろすのだそうです。
冬をどう越すか ということも良いブドウを造るための一つの重要な要素なのですね。