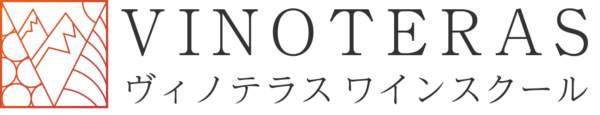この記事では、ソムリエ・エキスパートに合格する為の勉強法と資格の試験概要を詳しくご紹介します。
ワインの専門職であるソムリエ。ビストロやレストランでゲストの好みや注文した料理に合わせたワインを提案、サービスまでこなすのがソムリエです。飲食店のプロフェッショナル資格として是非取得したい資格ですね。一方飲食店のサービスマンでなくても、ソムリエに匹敵する知識を持ち合わせているのがワインエキスパート資格です。
※ソムリエ・エキスパート(以下ソムリエ)
目次
◆ソムリエ資格を取得する試験についての概要
1,ソムリエ試験とは?
2,ソムリエ試験の受験資格って?
3,ソムリエ試験はどれくらいの合格率?
4,ソムリエ試験ってどんな内容?
5,ソムリエ試験はいつ開催?どこが受験会場?
◆ソムリエ資格を取得す絶対合格したい!どれくらい勉強したらなれる?
◆ソムリエ試験に合格するための方法3選
1,ワインスクールに通い対面で学ぶ
2,時代はオンライン学習!オンラインワインスクールで受講
3,独学
◆ソムリエ資格を取得する試験についての概要
ソムリエ資格を取りたい!そう思ったらまずソムリエ試験とはどのようなものかを知っておきましょう。試験の概要をしることで取得にむけて対策をたてられます。
ソムリエ資格試験について概要をまとめてみました。
1,ソムリエ試験とは?
日本で最も有名なソムリエ資格は一般社団法人日本ソムリエ協会のソムリエ資格です。
ソムリエとはフランスやイタリアではレストランサービスの花形とされており、日本でもおなじくスタイリッシュな職業と認知されています。それだけに、ソムリエはレストランでワインを担当するだけではありません。ワインを中心としたアルコール飲料全般に関する幅広い知識。又、テイスティング技術が求められています。
この記事では料飲のプロを育てるために毎年開催されている一般社団法人日本ソムリエ協会のソムリエ資格試験についてお伝えします。
主に一次試験に合格する為に必要なことを中心にご紹介しています。
2,ソムリエ試験の受験資格って?
ソムリエ試験を受験するには飲食店(ワイン及びワイン以外のアルコール飲料を提供している)において3年以上のサービス経験があり、一次試験基準日時点で従事していることが条件として含まれます。又、一次試験基準日時点(8月31日)で満20歳であることも条件です。
但し、日本ソムリエ協会の会員歴が2年あれば、飲食店サービスの経験が2年以上で受験できます。
3,ソムリエ試験はどれくらいの合格率?
ソムリエ試験の合格率については近年3年間の平均は30%ですが、
2023年度の合格率は一気に下がり17.7%となっています。
スクールの充実やオンラインやタブレット、スマホなどで学習コンテンツの充実も合格率アップの要因と言えるでしょう。
とは言え合格率30%代の狭き門です。ストレート合格を目指すならしっかりとした対策が必要ですね。
4,ソムリエ試験ってどんな内容?
現在のソムリエ試験は三次試験まであります。(ワインエキスパートは二次試験まで) 試験内容は以下の通りです。
ソムリエ教本の内容からの筆記試験です。CBT方式と呼ばれるコンピューターを使った試験方式でマウスやキーボードで回答します。
こちらはテイスティング問題です。 ソムリエ資格については3銘柄、ワインエキスパート資格については4銘柄を答えます。
スティル・ワインについて外観・香り・味わい・その他の項目(適正温度、グラス選択など)、結論(品種、収穫年、生産国)についてコメント語群・結論選択肢の用紙から選んで回答しなければなりません。 試験の時間はテイスティング40分、論述20分(論述は3次試験に含む)の計1時間です
サービス技術と論述の審査が行われます。二次試験の回答が論述となるので、実際は実技審査のみ行われます。10人前後から数十人まで、会場の規模にあわせて同時審査されます。
指定のワインが告げられ、実践さながらにオーダーの復唱や道具をサービストレイに載せて移動、道具を配置します。ワイン抜栓からデキャンタージュ(ワインボトルから専用容器に移し替える作業)。そこからホストテイスティングまでが大きな流れです。
会場に入れば、道具の配置や動線などをチェックしておくとスムーズに動けます。
5,ソムリエ試験はいつ開催?どこが受験会場?
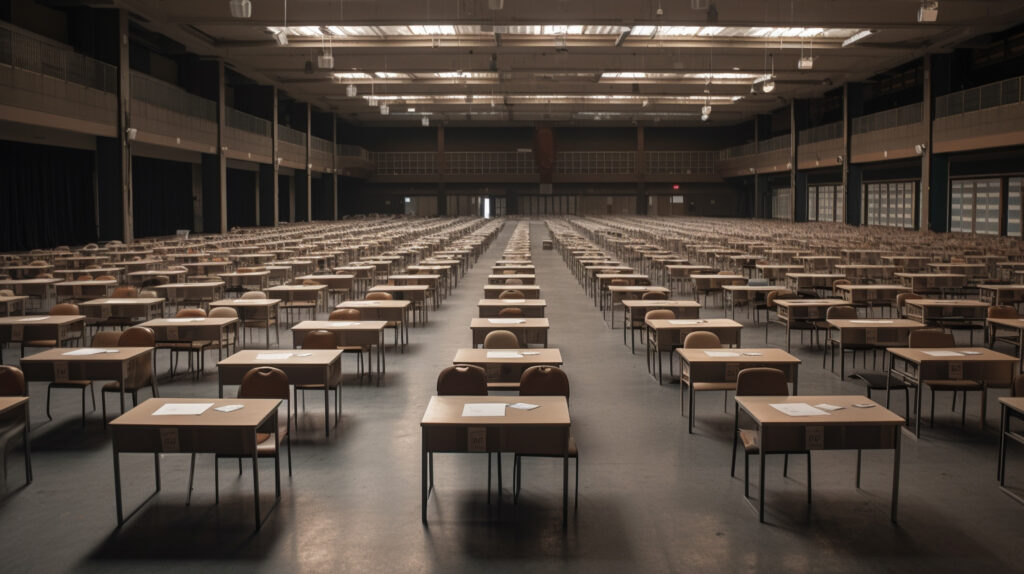
ソムリエ試験は全国で受験が可能です。二次試験、三次試験はテイスティングや実技をともなうので大きなホテルが会場となっています。
一次試験:毎年7月~8月全国47都道府県内の指定会場
二次試験:毎年10月全国16か所の指定会場
三次試験:毎年11月全国16か所の指定会場
一次試験の場所は受験者が選ぶことができます。WEBで事前に予約をしましょう。
◆絶対合格したい!どれくらい勉強したらなれる?
ソムリエ資格を取得するためには幅広い知識が必要です。一般的には、知識ゼロの方が資格取得までの勉強時間は400自時間と言われています。 夏の7月もしくは8月の一次試験を同年の1月に勉強を開始した場合。 平均して1日2時間勉強をすれば420時間取り組める計算になります。
出題はソムリエ教本からされるのでまずはそちらで勉強範囲の概要を知っていくのがおすすめです。その後は問題集などが沢山出版されています。
出題範囲が広いのでしっかりと自分に落とし込んでいくことが必要です。
飲食業に従事していてある程度ワインやアルコール飲料の知識をもっていたり、サービス経験があったりすれば勉強時間は違うでしょう。
仕事や家庭環境によっても個人差がありますが、できるだけ多くの時間を使った方が合格率はあがっていきます。
◆ソムリエ試験に合格するための方法3選
ソムリエ試験合格の最大の壁。それは一次試験突破です。 言い換えれば一次試験さえ突破すればグッと合格率はあがります。 あなたに合った勉強法をさがして下さいね。ここでは3つの方法を紹介します。
1,ワインスクールに通い対面で学ぶ
知識ゼロからスタートを不安に感じる方にはおすすめしたい方法です。 なぜならばワインスクールではワイン知識と共にテイスティング技術が身に付くからです。 講座に関連したワインテイスティングが付いてくるのでしっかりと体系的に学べます。 また、三次試験のサービス講座もあり合格までのサポートも手厚くなっています。
独学であれば計画通りに学習を進めるのが難しい!そう感じるあなたはワインスクールがおすすめ。ソムリエ資格取得に特化したカリキュラムが用意されており深い内容で学習が進められます。決められた日程があるので学習スケジュールが組みやすいのも魅力的ですね。
ワインスクールに通うメリット
スケジュールがあらかじめ設定されているので、半強制的に学習をすすめられます。 また、通学で出会えるワイン仲間と顔を合わせて勉強できます。同じ志をもった仲間は心強いですね。
ワインスクールに通うデメリット
場所によっては通学に時間がかかり交通費がかかることもあります。移動時間のロスタイムが気になり自分のペースがキープできない可能性もあります。
2,時代はオンライン学習!オンラインワインスクールで受講
最近主流になりつつあるオンライン学習。自分の生活スタイルに合わせた受講が可能です。
通学同様の動画講座に小瓶などでテイスティングも学べます。もちろん合格までのサポートも手厚くなっています。
オンラインワインスクール講座のメリット
オンラインは好きな場所で受講できるのが最大のメリットです。近くにワインスクールがなかったり、遠かったりする方には是非おすすめしたい方法です。
また、殆どのオンラインワインスクール講座で過去の授業が繰り返し視聴できます。 様々な都合で受講できなかったとしても安心。復習や聞き逃しもカバーできますね。
メールなどで質問もできるので対面が苦手な方でも受講しやすい方法です。
オンラインワインスクール講座のデメリット
通学と違い個人学習なので他の受講生との交流が少ない事です。 コミュニケーションが苦手な方にはもってこいの方法ですが……
3.独学
これは費用面でいえば最強の方法です。しかし強い意志としっかりとした計画が必要となってきます。
サービス経験者である程度の知識をもった方や業界のかたであれば、この方法はおすすめできます。
独学のメリット
学習スタイルの自由度が高いことです。好きな時間に自分のペースで進められるのは最大のメリット。 仕事の都合上、スクール通学が難しいときでも工夫しだいでは学習できます。 納得の行く方法で費用を抑えて学習を進めることができます。
独学のデメリット
独学のデメリットは計画通りに進めないと挫折しやすい点にあります。仕事がいそがしく思った以上にやる気がおきないといったこともあります。モチベーションの維持が課題。
費用が抑えられる分、最新の情報を自分で集める必要があります。スクールに比べると合格率が低くなってしまいます。 また、二次試験に必要なテイスティング技術なども自ら習得が必要です。
自ら購入したりワインバーや知り合いを頼ったりなどの工夫が必要です。
◆合格までに準備は何が必要?費用はどれくらい?
ソムリエ試験に合格する為にはワインスクールの受講料や参考書、テイスティンググラスやソムリエナイフなど必要なものは沢山あります。 ここではワインスクールに通うことを前提に必要なものをピックアップしました。 また、それらにかかる費用も一緒にご紹介します。
ソムリエ試験を受けるまでの費用
ソムリエ資格の勉強までに必要な準備があります。 スクールであっても独学であっても以下の準備は必須です。
【受験料】
一般社団法人日本ソムリエ協会に受験の申し込みをしたら受験料の準備が必要です。 『会員』と『一般』では費用が異なります。昨年度の2023年の受験料をお知らせします。 (1名様料金・教本代・税込)
一次試験から受験される方
1回受験 29,600円(一般) 20,380円(会員)
2回受験 34,440円(一般) 25,220円(会員)
二次試験から受験される方
14,210円(一般) 7,300円(会員)
三次試験から受験される方
7,100円(一般) 3,650円(会員)
【ソムリエ教本】
受験の申し込みをすると一般社団法人日本ソムリエ協会から送付されます。これは受験料にふくまれており改めて購入の必要はありません。
ワインスクールでは参考書や問題集を購入する必要はありませんが、独学の場合は自分で用意する必要があります。ブドウの品種や品質分類からテイスティング、ワインの産地や歴史、管理や販売についてまでもが網羅されています。
基本的には教本をもとに出題されるので試験までは相棒のようなものですね。
【参考書や試験対策問題集】
毎年最新版の予想問題集などの対策問題集が数多く市販されています。
ワインスクールに通うならばテストがあったり専用テキストが用意されたりしているので安心です。
独学で学習する場合は自ら購入する必要があります。
価格は2,000円前後が多く、複数試すことをおすすめします。
ソムリエ協会から発行される教本とは違い、市販の参考書は図解でわかりやすいものが多く発売されています。よく出る問題や項目、最新の傾向などを詳しく教えてくれます。 試験対策の問題集は間違いやすい点などもわかりやすくまとめてあるのでおすすめです。
書店で実際に内容を確認して納得のいくものを使っていきましょう。
◆通学とオンラインにかかる受講料ってどれくらい?
ワインスクールに通うとなればどれくらいの費用か気になるところですね。一般的なスクールの受講料をまとめてみました。
通学のワインスクールの場合
基本的に入会金があり、5,000円程度。少人数制のスクールであれば学びも深いです。通常のクラスだと全部で15〜20回の講座があり150,000円〜となっていますね。
教本などはセットになっている事が殆どですが、教材は別途費用が必要なスクールもあります。事前にHPなどでしっかりと調べておくとよいでしょう。
オンラインワインスクールの場合
受講コースにもよりますが、単発で受講可能なスクールもあります。費用は5,000円〜で、受けたい講座を自分で選択することができます。通学よりお手頃なものもあります。
パソコンやタブレットを開けば受講できるのは、忙しい人にはうれしいですね。
▼関連記事▼
【2024年度最新版】
ソムリエ・ワインエキスパート試験対策が学べるワインスクール比較
◆これは確実!ソムリエ試験に合格できる為の工夫
ソムリエ試験は合格率が30%代。簡単に合格できる資格ではありませんね。
そのため効率的に学習をすすめる必要があります。
ソムリエ試験に合格するための確かな工夫をご紹介したいと思います。
ここから始まるソムリエ教本
一般社団法人日本ソムリエ協会から送られてくるソムリエ教本。これが試験のベースとなります。 全て暗記するのは無理があります。まずは全体をおおまかに把握しましょう。 どれくらいの内容を頭にいれないといけないかの目安になります。 全体の把握をすれば学習計画が立てやすく、漏れもなく学習できるのでおすすめします。
自分の学習スタイルを作る
資格の勉強には様々なスタイルがあります。
問題集やテキストを使うのが得意な人、動画などを見て視覚的に覚えていくタイプ。 あなたにとって頭に入ってきやすい方法を選びましょう。
そしてその方法をひたすら繰り返すのです。これが一番確実な方法です。
◆苦手な分野は何?問題集を解いたらわかる弱点
なるべく同じ問題集を繰り返し解く事をおすすめします。同じ問題集を解くことで得意分野と苦手分野を自覚する事ができます。復習必要な箇所がわかり効率的に勉強ができます。
ソムリエ試験対策の問題集は書店で様々な種類が販売されています。実際に解いてみてあなたに合った問題集を1冊だけ選びましょう。
問題集によって解説が違ったり、構成が違ったりします。色々な問題集に手をだすと混乱する可能性もあるので、同じものを繰り返し解くことをおすすめします。
最近はどんな傾向?問題集で出題傾向を知る
ソムリエ試験には出題傾向があります。最大の目的「試験合格」に近づくためには傾向を知ることが近道となります。
過去問などから問題の傾向を把握してピンポイントに学習するのが効率的ですね。
あくまで傾向なので出題頻度の低い問題が出される可能性があります。
しかし、そのような問題は大きく合格を左右するようなボリュームで出題はされないのでご安心下さい。
◆一次試験〜三次試験それぞれの勉強方法を知りたい!
ソムリエ試験合格にはどのような学習スタイルをとっても自らの努力が不可欠です。 少しでも合格率があがる効率の良い勉強方法を取ることで、あこがれていたソムリエ資格があなたのものになります。 試験当日までの勉強方法について、おさえておきたいポイントをまとめました。
まずは情報収集から
一般社団法人日本ソムリエ協会が開示している試験概要をチェックしましょう。 どのような試験内容なのか?試験日まではどれくらいの期間があるのか?しっかりと把握しておく事が重要です。そこからどういった学習をすればいいか分かります。
ソムリエ試験の勉強をスタートして、いきなり問題集や参考書を開いて勉強を始めるのは効率が悪い方法です。ソムリエ試験の出題範囲は非常に幅広いので、情報をしっかりと集めて傾向を知っておくことが重要となります。
試験当日までのスケジューリングが重要
ある程度の情報が集まれば学習スケジュールを組みましょう。本番までどれくらいの期間があるのか?1年と3か月では当然、勉強の仕方が変わります。
まずは教本を一通り把握する期間、問題を解いて得意や苦手分野を知る期間などおおまかにスケジュールを立てる事でしっかりと合格へのイメージをつくりましょう。
仕事をしながらであれば忙しくなりなかなかスケジュール通りに行かないこともあります。体調不良などもあるかもしれません。余裕を持ったスケジュールで取り組めると安心ですね。
ワインに親しむ

普段からワインに触れる機会が少ない人はテキストの内容だけではなかなか理解しにくいものです。
一次試験に気を取られてテキストや問題集の勉強ばかりしがちです。二次試験のテイスティング対策として、普段から少しずつでもワインを口にして、ワインに親しんでおきましょう。ワインの味わいや香りなども勉強しておくといいですね。 文面だけで理解できない時は一旦テキストを閉じて実際ワインにふれるのも重要です。
レストランにいってワインを注文してみたり、ワインショップで店員さんに質問をして説明を受けたりするとより理解が深まります。
自身が体験することでテキストや問題集で説明されている内容がすんなり頭に入ってきやすいのでおすすめです。
実践!模擬試験を受ける
ヴィノテラスワインスクールでは実践形式の模擬試験を行っています。
これまで学習した内容がどれくらい頭に入っているのか?実際問題を解いてみると客観的に判断することができます。しかし問題集やテストなどでは本番で同じように実力を発揮できるかわかりません。
模擬試験では本番と同様に制限時間があります。実際の試験と近い環境で取り組めます。
実際どれくらいで問題が解けるのか?どのような問題なのか?時間配分もわかるようになり、問題のレベルも把握できます。
得意な分野で点が取れる、苦手な分野で点が取れないなどが確認できますね。本番までにしっかりとカバーをしていきましょう。
まとめ
さああなたはどんなふうに勉強しますか? 合格率30%代のソムリエ試験は思っているより努力が必要です。しっかりと情報を集めて出題傾向を知って対策をたてましょう。



ライター 鎌田 陽(かまだ ひかる)
元ホテルマン。レストランを中心にソムリエとして勤務。ワインに関わって約10年、メーカーズディナーなどのイベントを企画・開催「ワインは人を幸せにする飲み物」をモットーにフリーランスライターやインポーターとして活動中!